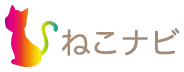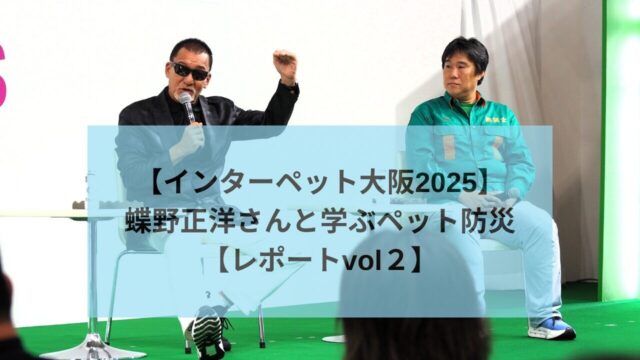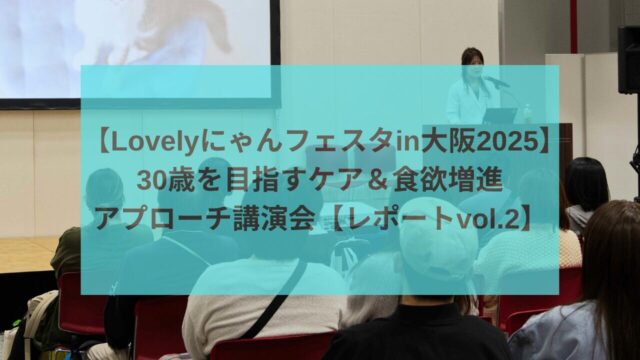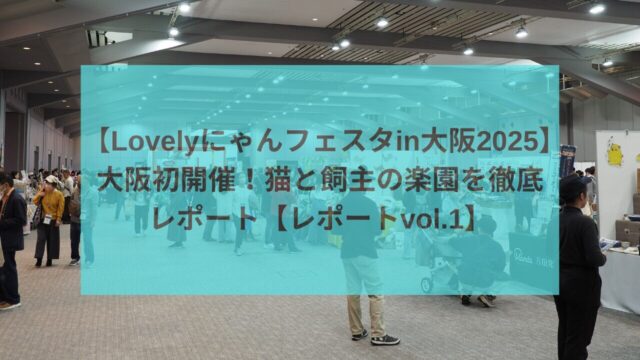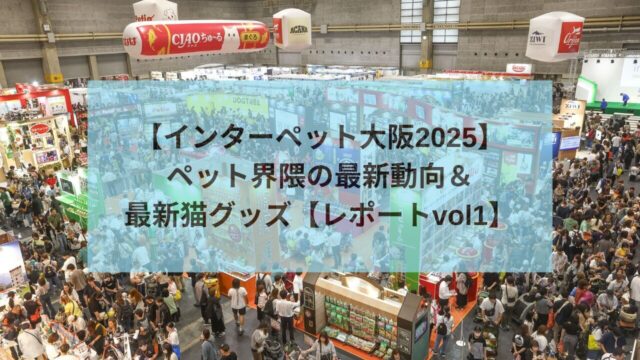西日本最大級のペット産業見本市「第3回 インターペット大阪」が、2025年6月13日(金)から15日(日)の3日間、インテックス大阪1-3号館で開催されました。
インターペット大阪2025の2日目・14日(土)には、猫の健康に関する2つのセミナーが開催されました。一般社団法人AIM医学研究所の宮崎徹理事長による猫腎臓病治療薬の最新進捗報告と、愛玩動物看護師による「おうちでこそ見えるサイン」についてのセミナーです。今回は両セミナーの内容をお届けします。
歴史的快挙!猫腎臓病の治療薬・AIMの治験がついに開始

30年のAIM研究がついに実を結ぶ
「30年間研究してきたAIMが、ようやく治験に入ることができました。これは皆さんの応援があったからこそです」。
一般社団法人AIM医学研究所の宮崎徹先生は、感無量の面持ちでセミナーを始められました。元人医である先生は、医学部時代に腎臓病の患者さんを目の当たりにし、「治らない病気を治したい」と強く思ったそう。そこから始まり紆余曲折を経てたどり着いた猫の腎臓病研究が、ついに実用化への最終段階に到達したのです。
AIMの詳しい作用機序については、昨年のインターペット大阪2024での詳細レポートで「山火事」の例えを使って分かりやすく解説していますので、ぜひご参照ください。今回は、その研究がどこまで進んだのか、そして私たちの手元に届くまでの道のりについて最新情報をお伝えします。
治験への道のり…猫腎臓病研究の現在地と猫の飼い主さんたちの期待
AIM薬の開発は、基礎研究から始まって様々な段階を経て進められてきました。まず長年にわたる基礎研究でAIMの働きを徹底的に解明し、その後に動物実験で安全性と有効性を確認。そして2024年6月から臨床試験前の最終安全性試験を実施し、ついに2025年5月には実際の猫を対象とした治験が開始されました。
この治験開始に向けて、全国から寄せられた期待は想像を超えるものでした。宮崎先生は当時を振り返ります。
「治験参加者をSNSのXで募ったところ、2月から4月にかけて、800匹を超える猫ちゃんと飼い主さんから参加希望をいただいたんです」
北は北海道から南は九州まで、全国各地から561匹の猫たちが血液検査を受けました。しかし、治験には厳格な条件があります。猫の腎臓病には進行度によってステージ1から4まで分類されており、今回の治験では特定のステージの猫のみが対象となるため、参加できる子は限られていました。
「ステージの中でも、本当に狭い範囲の進行度の猫ちゃんたちを集める必要がありました。皆さんにお待ちいただいているのに、全員に参加していただけないのは本当に申し訳ない気持ちでした」。
それでも、多くの猫と飼い主さんたちが協力したおかげで、予定通り5月から治験を開始することができたとのこと。宮崎先生は感謝の気持ちを何度も表現されました。
猫腎臓病の治験は順調に進行中、新薬は2027年春の実用化へ

現在、治験に参加している全ての猫たちがAIM注射を受けており、経過は順調に推移しているとのことです。猫ちゃんたちには年末まで継続的にフォローアップを行い、AIMが実際に腎臓の病状を消し、残っている腎臓組織を元気にしているかどうかを詳しく調べていきます。
「来年2026年には農林水産省への承認申請を行います。審査期間を考慮すると、2027年春には皆さんのお手元にお届けできるようになると思います」。
長年猫の腎臓病に悩んできた多くの飼い主さんにとって、ついに具体的な希望の光が見えた瞬間でした。
猫が30歳まで生きる未来への期待
セミナーの締めくくりで、宮崎先生は改めて研究への思いを語りました。
「30年間、『今までになかった病気を治す』というただこれだけのために研究を続けてきました。医師として、治せない病気をずっと見ているだけという状況がどうしても受け入れられなかったんです。でも、ようやくここまで来ることができました」。
猫の平均寿命は現在15歳前後ですが、腎臓病という最大の死因を克服できれば、セミナータイトルにもある通り「猫が30歳まで生きる日」も夢ではないかもしれません。宮崎先生の30年にわたる研究と、全国の猫ちゃんと飼い主さんたちの期待が、ついに実を結ぼうとしています。
愛玩動物看護師が教える「おうちでこそ見える病気のサイン」

続いて開催されたのは、訪問動物看護ステーション「ゆりかご」の磯田拓也先生と、「こころ鳳ペットクリニック」の永田稚花愛玩動物看護師による健康管理セミナーです。病院では見ることのできない、家庭だからこそ観察できる重要なサインについて詳しく解説されました。
動物たちは確実に不調を「声」に出している
「動物たちは言葉で不調を訴えることはできませんが、確実に『声』を出しています。その声は言葉だけでなく、行動や体の変化、普段とは違う動き方として現れるんです」。
磯田先生はこう切り出しました。訪問動物看護の現場では、動物病院では見ることのできない自然な状態の動物たちを観察することができます。そこで気づくのは、動物たちが実に多くのサインを出しているということです。
病院での診察時には、動物たちは緊張や興奮状態にあることが多く、普段の様子とは異なる行動を取りがちです。しかし家庭では、リラックスした自然体の状態を観察できるため、ささいな変化に気づくことができるのです。
食べ方・飲み方に現れる病気の重要なサイン

飼い主さんは「完食していますよ」と言うことが多い一方で、実際に観察してみると食べ方に変化が現れていることがよくあります。以前は一気に食べていたのに、途中で休みながら食べるようになったり、食べるスピードが明らかに遅くなったりといった変化です。
これらの変化は単なる加齢によるものかもしれませんが、歯の痛みや口の中のトラブル、あるいは全身の不調を示している可能性もあります。田中看護師は特に歯科疾患について注意をしてほしいと話しました。
「犬や猫の歯科疾患はとても多いのですが、動物たちは口の痛みを我慢してご飯を食べ続けることが多いんです。そのため、気づいた時にはかなり進行してしまっていることもあります」。
水分摂取についても重要なポイントがあります。多くの飼い主さんが「お水をあまり飲まないんです」と心配される一方で、実は注意すべきは飲みすぎの方だといいます。
・腎臓病の初期症状として多飲が現れる
・糖尿病でも水をよく飲むようになる
・甲状腺機能亢進症の兆候としても多飲がある
「以前と比べてよく飲んでいるなと思ったら、できれば水の量を測って記録していただき、獣医師に相談してください。病気の早期発見につながる可能性があります」
呼吸の変化は命に直結する重要なサイン

呼吸の観察は特に重要。動物病院では緊張により呼吸が乱れがちなため、家庭での気づきは貴重なものとなります。特に注意すべきは、寝ている時やリラックスしている時の呼吸です。
正常な呼吸では胸の動きだけで十分な酸素を取り込めますが、心臓や肺に問題がある場合、腹部まで使った全身での呼吸が必要になります。これは医学的には「補助呼吸筋の使用」と呼ばれる状態で、呼吸困難の重要なサインです。
また、犬と猫では咳の出方も異なります。犬の咳は最後に「えづく」ような仕草を伴うことが多く、飼い主さんが「気持ち悪そうにしている」と表現することがよくあります。一方、猫の咳は人間のようなものとは異なり、むせるような感じで現れます。
「呼吸の異常は心臓や肺の問題に直結することが多く、緊急性が高い場合があります。普段と明らかに違う呼吸をしていたら、早めにご相談ください」。
寝方や体勢の変化が教えてくれる病気の予兆

動物病院では動物たちがリラックスして自然な姿勢で寝ることは難しいため、家庭での寝方の観察は特に貴重な情報源となります。磯田先生は印象的なエピソードを紹介してくれました。
「いつもはうつ伏せで寝ていた猫ちゃんが、最近は座ったような体勢でしか寝なくなったという変化がありました。胸の音を聞いてみると、心音が少し遠く聞こえ、活動量も落ちていました。病院で検査してもらったところ、胸に水が溜まっている状態だったです」。
このように、寝方の変化から重篤な疾患を早期発見できることもあります。呼吸が苦しい時、動物たちは楽な体勢を自分で見つけて寝ようとするため、普段とは異なる寝方をするようになるのです。
排泄は最もわかりやすい体調のバロメーター
排泄物は「体の外に出てきた瞬間の情報」として、体調の変化が最も分かりやすく現れる部分です。回数、量、色、状態など、様々な要素が健康状態を反映します。田中看護師は、排泄に関する相談が動物病院でも非常に多いと話してくれました。特に泌尿器疾患は緊急性が高いことも多く、普段からの観察が重要です。
排泄の変化を正確に伝えるためには、可能であれば写真を撮影しておくことがおすすめです。色や状態を言葉で説明するよりも、視覚的な情報の方が獣医師にとって診断の助けになります。
動物の行動や表情に現れる心と体の変化

「最近散歩に行きたがらなくなった、活発でなくなった」という変化についても、単純に足腰の問題だけとは限りません。心臓病の進行、視力や聴力の低下、認知機能の変化、薬の副作用によるストレスなど、様々な原因が考えられます。
特に重要なのは、視力が低下してきた場合の対応です。多くの飼い主さんが安全を考えて家具の配置を変えたり、段差をなくそうと大幅な模様替えをしたりしがちですが、これは逆効果になることが多いのだとか。
「犬や猫は『地図』を頭の中に持っています。レイアウトを大きく変えてしまうと、その地図が使えなくなって、かえって動けなくなってしまうんです」。
表情や目の力の変化も重要なサインです。動物病院では緊張で表情が変わってしまうため、普段の自然な表情を知っているのは家族だけです。目の輝きがなくなったり、第三眼瞼(瞬膜)が出てきたりする変化は、脱水や体温低下などの重要なサインである可能性があります。
ペットの変化に気づいた後の対応:観察・工夫・相談
何らかの変化に気づいた時、まず大切なのは冷静な観察です。「何が起こっているんだろう」とパニックになりがちですが、深呼吸をして一呼吸置き、じっくりと状況を観察することが重要です。
食欲が落ちた場合でも、様々な工夫を試してみることができます。フードを少し温めてみる、冷やしてみる、好きなもののトッピングを加える、食器の高さを変える、水の種類を変えるなど、小さな変化が大きな改善につながることもあります。
そして最も重要なのは、早めの相談です。「こんなことで相談してもいいのかな」と躊躇する飼い主さんが多いものの、両看護師は口を揃えて言います。
「何もなければそれで良いんです。後で後悔するよりも、早めにご相談いただいた方が、結果的に動物たちにとって一番良いことが多いんです」。
ペットの様子を記録する重要性と訪問看護の可能性

現代では、スマートフォンで手軽に写真や動画を撮影できるため、症状の記録が以前よりずっと簡単になりました。歩き方の変化、咳の様子、排泄物の状態など、言葉では伝えにくい症状も視覚的に記録できます。
「写真や動画があると、獣医師への説明が格段に正確になり、診断の精度も上がります」。
また、磯田先生からは訪問動物看護の可能性についても紹介がありました。自宅での体調チェック、環境の見直し、生活全般のサポート、そして家族の心のケアまで、病院では提供できない包括的なサポートが可能です。
「病気の治療だけでなく、生きていくその時間をどう支えるかを一緒に考えていきたい。不安を抱えたまま一人で頑張りすぎないで、必要な時は私たちを頼ってください」。
まとめ
 写真提供:インターペット大阪
写真提供:インターペット大阪今回のインターペット大阪2025では、猫の腎臓病治療における歴史的な進展と、日常の健康管理の重要性という両面から、猫の健康について深く学ぶことができました。AIM薬の実用化への道筋が明確になった一方で、それまでの期間も、そしてその後も、私たち飼い主による日々の観察と適切なケアが猫ちゃんたちの健康を支える基盤となることが改めて確認されたと言えるでしょう。
次回開催情報
インターペット東京2026
開催日:2026年4月2日(木)〜5日(日)
会場:東京ビッグサイト
インターペット大阪2026
開催日:2026年6月19日(金)〜21日(日)
会場:インテックス大阪(会場規模を拡大予定)
Vol.1はこちら:【インターペット大阪2025】ペット界隈の最新動向&最新猫グッズをお届け【レポートvol.1】
Vol.2はこちら:【インターペット大阪2025】蝶野正洋さんと学ぶペット防災【レポートvol.2】